6月の休診日・矯正日について
6月の休診日は、6月1日(日)、15日(日)、29日(日)となります。 また、6月の矯正日は6月7日(土)、6月19日(木)となります。 よろしくお願い致します。
2025.06.05
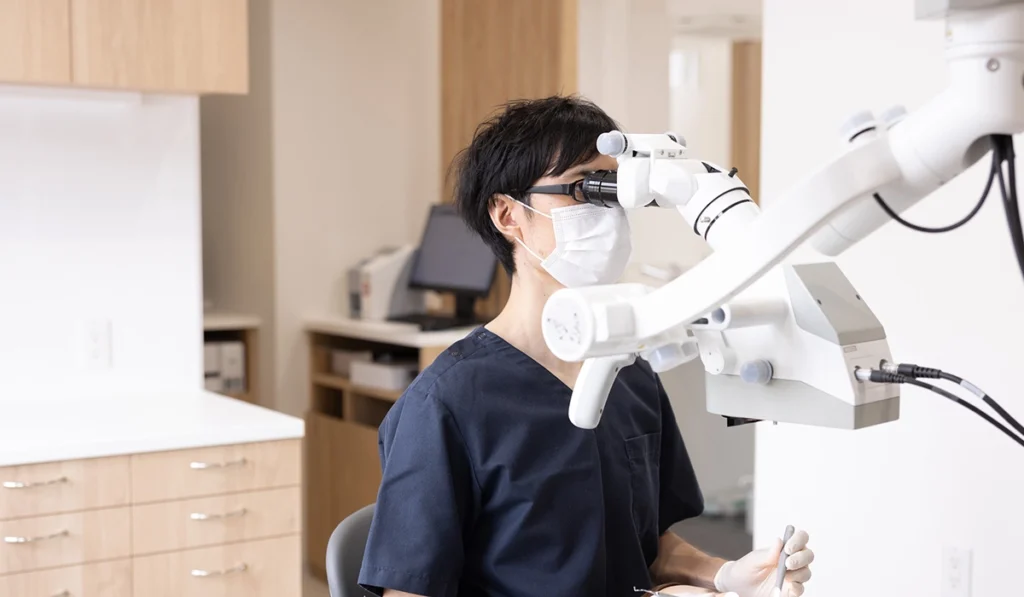


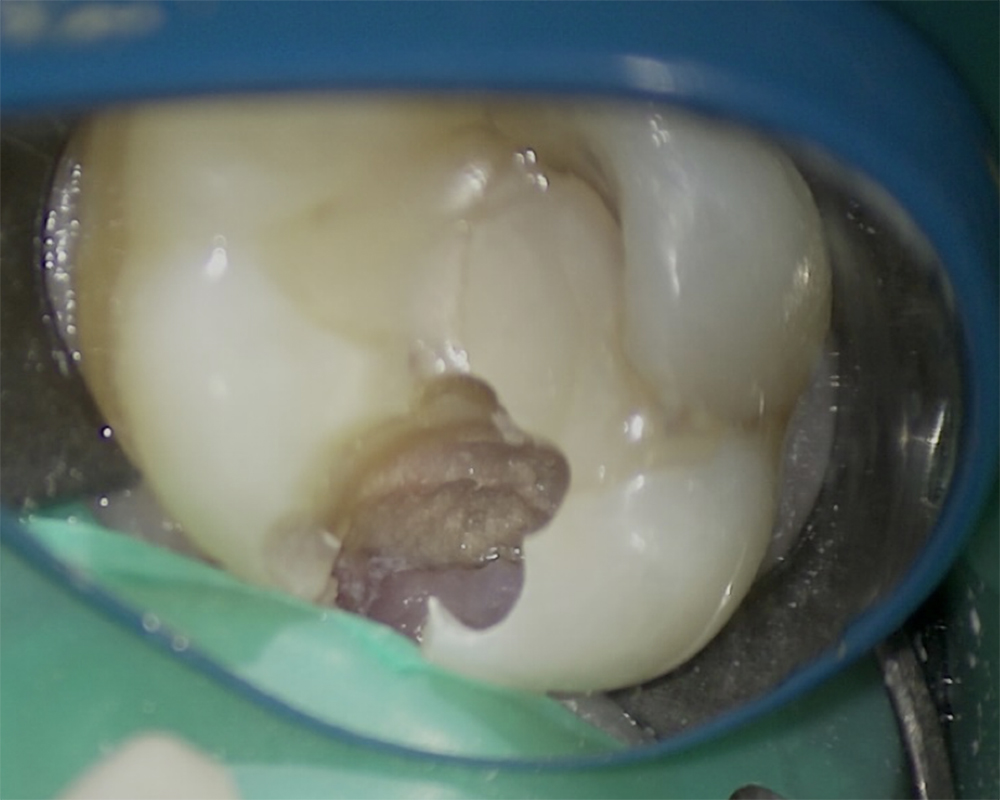
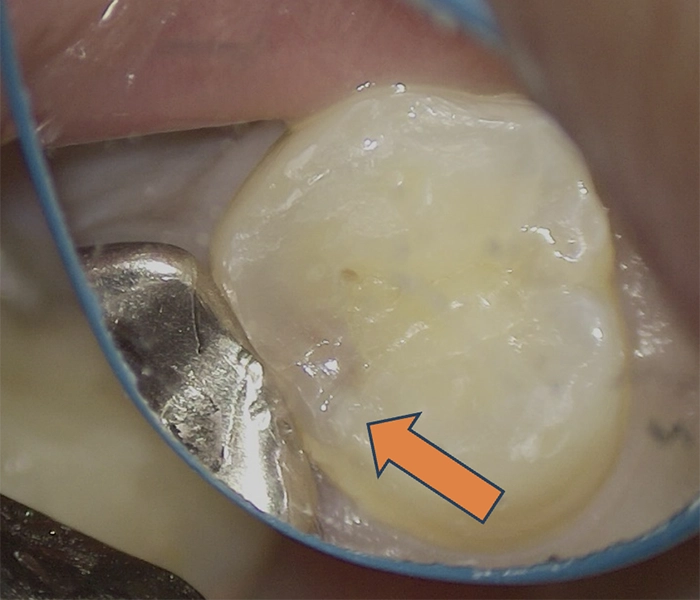

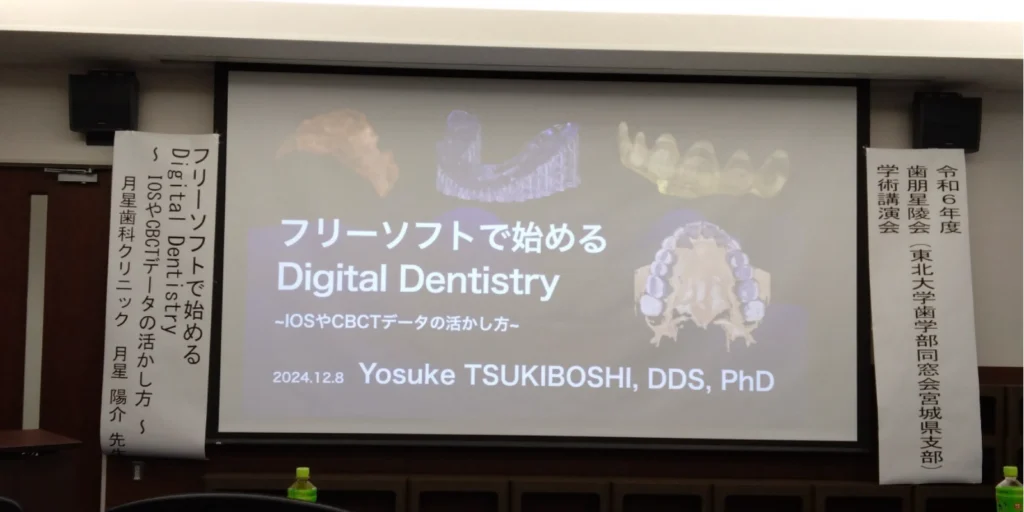
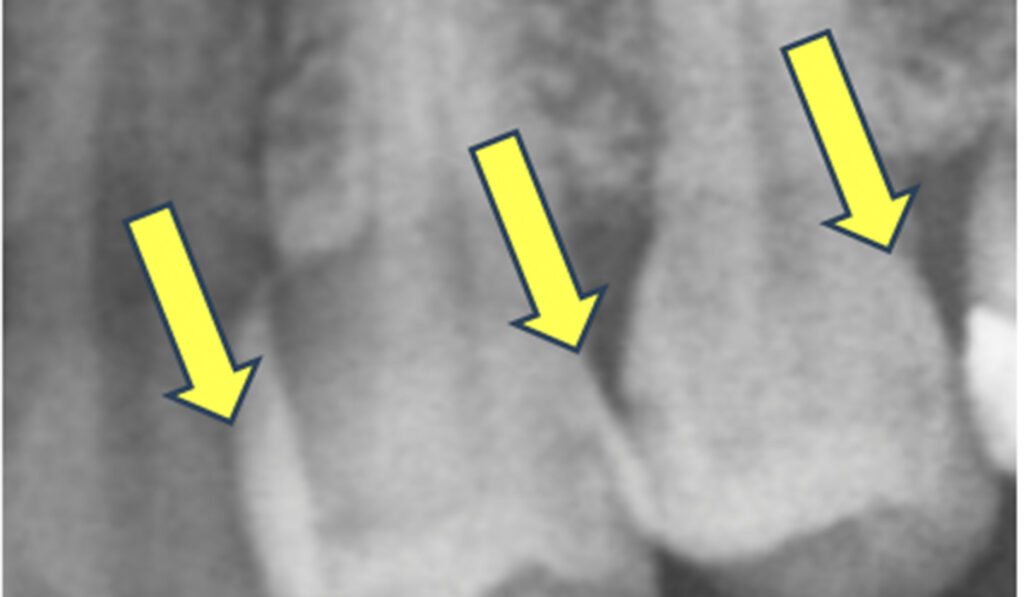

| 月火水木金土日 | |
| 09:30-13:00 | ×●●●●●● |
| 14:00-18:00 | ×●●●●※× |
【 休診日 】 月曜・祝日
※土曜日は17時まで
※最終受付は診療終了30分前になります。